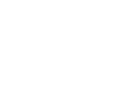クリニックレター
2025.04.01
クリニックレターvol.111: 血液をサラサラにする薬って何?
皆さん、こんにちは。当クリニックは、循環器内科を標榜しており、狭心症、不整脈、脳梗塞の患者さんを多数診察しています。よく、患者さんとの会話の中で、「血液サラサラの薬を飲んでいます」と聞くことが多いです。実はこの"血液サラサラの薬"にはいくつか種類があり、使う病気や目的によって異なります。今回はその違いや使用される病気について、簡単にご説明します。
血液サラサラの薬=抗血栓薬
血栓(けっせん)とは、血管の中でできる「血のかたまり」のこと。この血栓が脳や心臓の血管をふさぐと、脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる病気を引き起こすことがあります。
その予防や治療に使われるのが「抗血栓薬(こうけっせんやく)」です。
抗血栓薬は大きく分けて2種類あります。
動脈硬化により血管の中に血栓が出来て血液の流れが止まってしまっている様子を描いた断面図と血液がサラサラになっている血管の断面図です。
抗血小板薬(こうけっしょうばんやく)
これは、「血小板」という血液中の細胞の働きを抑えることで、血栓ができるのを防ぎます。
主な薬の名前
- アスピリン(バイアスピリン®など)
- クロピドグレル(プラビックス®)
- プラスグレル(エフィエント®)
- シロスタゾール(プレタール®)など
よく使われる病気
- 心筋梗塞や狭心症(心臓の血管の病気)
- 脳梗塞(ラクナ梗塞など)の再発予防
- 冠動脈ステント治療後の血栓予防(心臓の血管)
抗凝固薬(こうぎょうこやく)
こちらは、「凝固因子」という血液を固める成分の働きを抑えることで、血栓をできにくくします。
主な薬の名前
- ワルファリン(ワーファリン®)
- 直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)
・エドキサバン(リクシアナ®)
・アピキサバン(エリキュース®)
・ダビガトラン(プラザキサ®)など
よく使われる病気
- 心房細動(しんぼうさいどう)という不整脈による脳梗塞の予防
- 深部静脈血栓症(DVT)や肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)
- 心臓に人工弁(機械弁)が入っている方の血栓予防
薬の違い=使う目的の違い
抗血小板薬
- 主に効く場所:動脈(高圧の血管)
- よく使う病気:心筋梗塞・脳梗塞など
抗凝固薬
- 主に効く場所:静脈・心臓内など
- よく使う病気:心房細動・DVT・肺塞栓
血が止まりにくくなる薬です
どちらの薬も「血を固まりにくくする」ため、ケガや手術のときに出血が止まりにくくなることがあります。
そのため、歯科治療や手術の前には、必ず薬を飲んでいることを伝えるようにしましょう。
まとめ
「血液をサラサラにするお薬」は、命を守るためにとても大切なお薬です。
心臓や脳の血管が詰まるのを防ぐことで、脳梗塞や心筋梗塞の再発を防いだり、命に関わる合併症を防いだりする役割があります。
ただし、これらの薬は「血が固まりにくくなる」という働きがあるため、
思わぬ出血(鼻血、あざ、尿に血が混じる、便に血が混じるなど)が起きることもあります。
そのため、以下の点に注意していただくことが大切です
- 他の病院や歯科を受診する際は、必ずこの薬を飲んでいることを伝えましょう。
→ 手術や抜歯の前に一時的に中止が必要になることがあります。 - 薬を自己判断で中止しないようにしましょう。
→ 飲まないことで血栓ができ、脳梗塞などを引き起こす可能性があります。 - 出血が続く、血尿が出る、黒い便が出るなど異変を感じたときは、すぐにご相談ください。