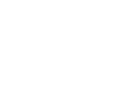クリニックレター
2025.03.17
クリニックレターvol.110 「アルコールと健康について考える」
今回は、多くの方の生活に関わる「アルコール(お酒)」について、最新の医学情報を交えながら、その良い面と悪い面について考えてみたいと思います。「お酒は百薬の長」ということわざがあるように、適量であれば心身のリラックス効果などが期待できます。しかし、飲み過ぎると健康を害してしまうことも事実です。以前にレターvol.91(2024年5月15日配信)でも「アルコール依存症について」詳しく解説しています。
今回は、アルコール依存症ではなく、アルコールが身体に与える影響や、お酒ごとの特徴について、最新の医学情報をもとにお伝えします。
アルコールの摂取による影響
日本肝臓学会の研究によると食事中の飲酒は、食事以外の飲酒よりも死亡率が低いという研究結果があります。また、国立国際医療研究センターの2024年の研究では、アルコールの飲み放題は問題飲酒と関連があるという研究結果も出ています。ですので、どんな時にお酒を飲んだかによって、体の中でアルコールがどのように処理されるかを知ることは、お酒と上手に付き合う上でとても大切なことになります。
アセトアルデヒドという物質
お酒を飲んだ時に肝臓での代謝で有害物質アセトアルデヒドという物質が体内で生成されます。これが実は二日酔い、頭痛、動悸の原因になります。アセトアルデヒドは体内にあると長期的に見ても良い影響がないため、体内で分解しなくてはなりません。ただ、日本人を含む東アジアの人々の約40%は、このアセトアルデヒドを分解する酵素(ALDH2)の働きが弱いという遺伝的な特徴を持っています。そのため、少量のお酒でも顔が赤くなったり、動悸がしたりというような症状(アルコールフラッシング反応)が出やすいと言われています。この体質の人とそうでない人と比べて、アルコールに関連する病気のリスクが高いことが、国立遺伝学研究所のデータにより判明しています。
ACイラストより
お酒の種類と生活習慣の関係
米国テュレーン大学の研究(2023年)によると、お酒の種類によって生活習慣に違いがあることが示唆されています。
ビール愛好家
- 健康的な食事(健康食指数) 49.3点
- 十分な身体活動をしている割合 42.2%
- 喫煙率 27.8%
ワイン愛好家
- 健康的な食事(健康食指数) 55.1点
- 十分な身体活動をしている割合 59.8%
- 喫煙率 10.0%
また、ビールは炭水化物が多い食品や加工肉と一緒に飲まれる傾向がある一方、ワインは肉や野菜、乳製品と一緒に飲まれることが多いという研究結果もあります。
※これらはあくまで統計的な傾向であり、すべての人に当てはまるわけではありません。
アルコールの健康への影響
① 良い影響
- 赤ワインに含まれるポリフェノール(レスベラトロール)には抗酸化作用があり、動脈硬化予防の可能性があります。
- 「フレンチパラドックス」(フランス人は脂肪摂取量が多いにもかかわらず冠動脈疾患が少ない現象)とも関連があると考えられています。
ポリフェノールについては、vol.105(2025年1月16日配信)「地中海式ダイエット」にて詳しく解説しています。
② 悪影響
- 肝臓への影響: 過度な飲酒は脂肪肝、肝炎、肝硬変の原因になります。(国立国際医療研究センター)
- 脳への影響: 判断力や記憶力の低下、アルコール依存症のリスク増加。
- がんリスク: 少量でもがんのリスクを高める可能性が指摘されています。(スペイン・マドリード自治大学 2024年報告)
適正飲酒量と蒸留酒の特徴
厚生労働省のガイドラインでは、1日の適量を 純アルコール量で男性20g、女性10g としています。しかし、最新の研究では「少量でも健康リスクがある可能性」が示唆されています。
純アルコール20gの目安
- ビール:中瓶1本(500ml)
- 日本酒:1合(180ml)
- ワイン:グラス2杯弱(240ml)
- ウイスキー:ダブル1杯(60ml)
蒸留酒(ウイスキー、焼酎、ジンなど)の特徴
- 糖質がほぼ含まれていない
- アルコール度数が高いため、適量を守る必要がある
- 日本糖尿病学会のガイドラインでは、糖質制限をしている場合でもアルコール自体のリスクは考慮すべきとされています
ACイラストより
蒸留酒(ウイスキー、焼酎、ジンなど)は、糖質がほとんど含まれていないのですが、アルコール度数が強いので摂取量には気を付けなくてはいけません。日本糖尿病学会のガイドラインによれば、ビール350mlには約10~15gの糖質が含まれていますが、同程度のアルコール量を含む蒸留酒にはほとんど糖質が含まれていません。このため、糖質制限を行っている方には蒸留酒が選択肢となるかもしれませんが、アルコールそのものの健康リスクは考慮する必要があります。
最後に
アルコールの影響は個人差が大きく、最新の研究では「少量でも健康リスクがある」との指摘も増えています。お酒を楽しみたい方は、以下のポイントを意識しましょう。
- 自分の体質を知り、適量を守る
- 週に2日以上は休肝日を設ける
- 食事と一緒にゆっくり飲む
お酒は文化や社交の一部ですが、健康リスクを理解し、適切に付き合うことが大切です。気になる症状がある場合は、医療機関にご相談ください。